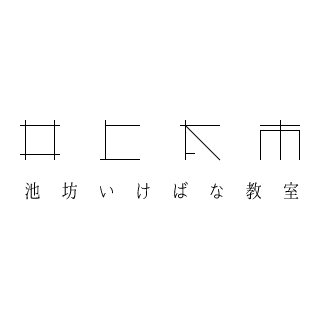池坊
いけばなには数多くの流派があります。その中で、当教室で学ぶのは「池坊(いけのぼう)」です。
現存する数ある流派の中で最も古いのが池坊。つまりいけばなの元祖が池坊なのです。
この池坊と言うのは、京都にある頂法寺(通称は六角堂)のお坊さんの名前です。池のほとりに住まいがあったので「池坊」と呼ばれるようになったそうです。
どのお寺でも仏様に花をお供えしていますよね。そんな中で、あの六角堂の池坊さんの立てる花は一味違うぞという評判が立ち、次第にいけばなと言えば池坊という風になっていったのです。

池坊いけばなの3つの様式
池坊のいけばなには大きく分けると3つの様式があります。
立花(りっか)
いけばなの最も古い様式です。神仏に祈る気持ちから起こった立てる花をルーツに発展しました。たくさんの種類の植物を使い、それらがそれぞれの役割を果たしながら調和します。豪華絢爛で複雑かつ洗練された姿になります。室町時代から江戸時代の前期にかけてその様式が整ったとされています。


生花(しょうか)
立てる花に対して、より軽やかな花としていける花がありました。そこから発展したのが生花です。江戸時代の中期に形式が整いました。立花とは対照的に、非常に少ない種類で生けます。簡素ですっきりとした姿が特徴です。床の間によく似合う花です。


自由花(じゆうか)
立花、生花は古い歴史があり型があります。音楽で例えるとクラシックにあたります。それに対して、いけばなの美感、考え方を踏まえた上で、自分で自由に創作するのが自由花です。環境に応じて形や飾り方を考えるので、日常生活に取り入れやすい様式だと思います。


いけばなってなんだろう?
花って綺麗ですよね。その綺麗な花を器に飾る、これがいけばなです。このときに、ただ色や形の美しさを見るだけでなく、花を生きているものとして扱うことがいけばなの特徴です。
自然の植物に目を留めたときのことを思い返してください。色や形などにひかれることもあると思いますが、それだけではないはずです。上に向かってぐんぐんと伸びている姿を見て、力強さや生命力を感じることがありませんか。あるいは、桜が散っていく姿を見て、儚さや潔さを感じたことがあるのではないでしょうか。
我々は植物を見て、単に色や形などの見た目だけに感動しているのではありません。植物の命、生きている姿に心を動かされているのです。
いけばなでは、そういう風に植物を捉えます。世界中に花を飾る文化はありますが、植物の生きている姿に注目をするのはいけばな独特の見方です。




花をいかす
このような考え方から、いけばなでは花をいかすということを大切にします。花が生き生きと弾んで見えるようにいけるのです。
では、具体的にはどうしたら花がいきいきと見えるのでしょうか。長い年月をかけて蓄積した様々な技がありますが、まずは最も大切な2つのことを伝えます。
間(ま)
1つ1つの植物の間に空間をとります。くっつくとお互いが寄りかかっているように見えますが、間を空けることで、1つ1つが自立して、自分の力で上に向かって伸びているように見えます。


表情をよく見る
生きているものは、同じものが1つとしてありません。同じ種類の植物であっても、それぞれ曲がり具合や葉の付き方、花の大きさなど微妙に違っています。色々な向きや角度から見て、どの姿で扱うと生き生きと見えるのかをよく観察しましょう。